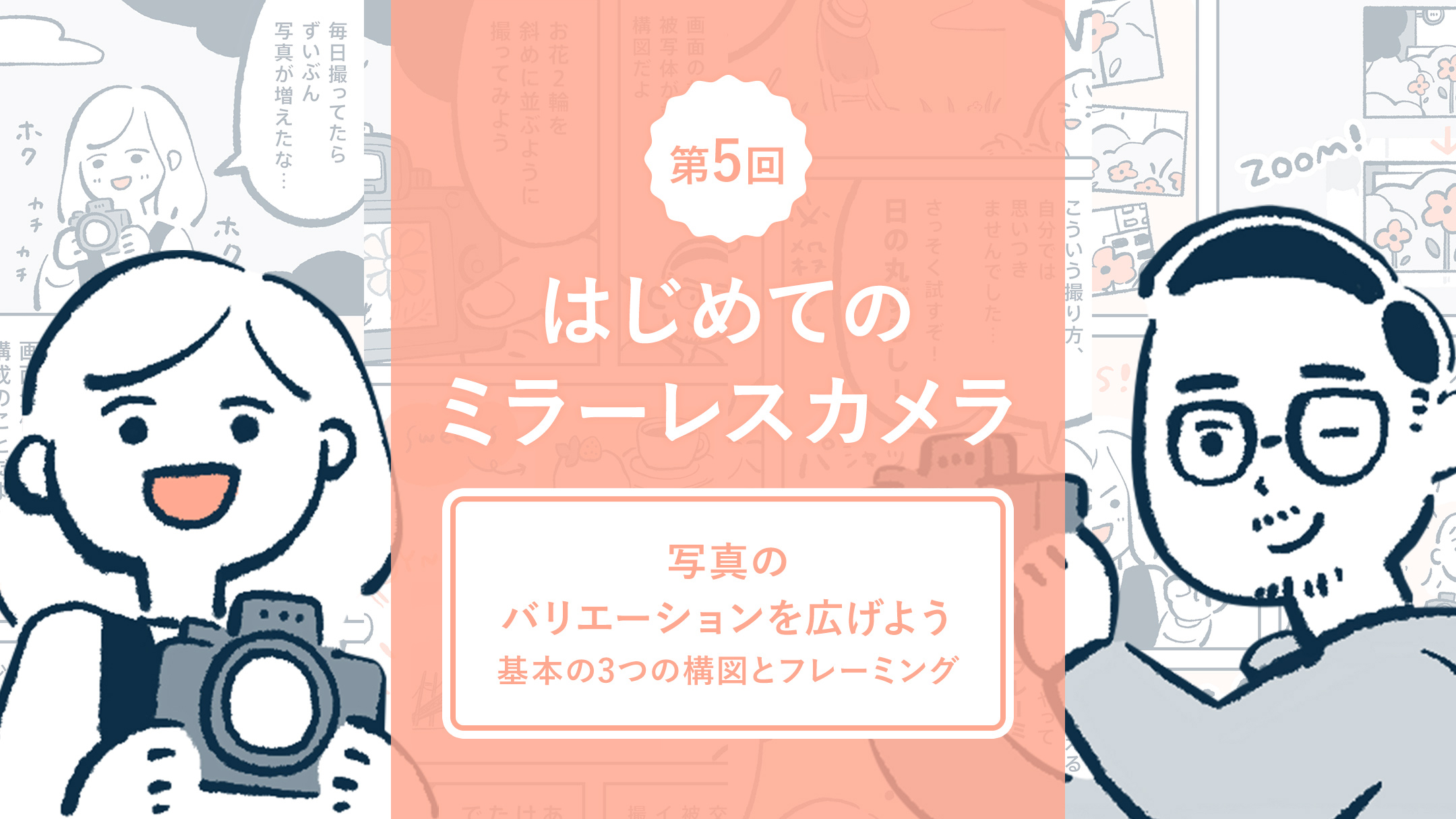
写真初心者のミナちゃんが、カメラや写真について学んでいく連載企画「はじめてのミラーレスカメラ」第5回。最近撮った写真を見返していたミナちゃん。すると写真を見た嵐田さんから「日の丸構図を使いこなしているね」とお褒めの言葉が! でも、日の丸? 構図? それって一体なんのこと? 撮影パターンを増やし、写真の印象を変化させる「構図」と「フレーミング」について学びます。

ミナちゃん
ミラーレスカメラ Z 50を持ち歩き、日々シャッターチャンスを模索!

嵐田さん
東京を拠点に、家族写真や都市光景を中心に撮影するフォトグラファー。




さらに詳しく!「構図」と「フレーミング」の基本と嵐田さん流、使いこなしポイント
被写体はひとつでも、「構図」と「フレーミング」をそれぞれ調整しながら撮影するだけで、写真のパターンを増やすことができます。
■構図
写真画面全体の構成のこと。構図を意識しながら撮ることで、撮影パターンを増やしたり、写真に変化をつけて表現の幅を広げたりすることができます。使う構図によって、同じ被写体でも趣の異なる写真に仕上げることができます。
多くの種類がありますが、覚えておきたい基本の構図は次の3つ。
1.日の丸構図

- 画面中央に被写体を置く。あらゆる構図の中でも最も基本的な構図
- モノを撮影すると、動きが止まったような静的な印象を伝えられる
日の丸ずらし構図
- 日の丸構図から、被写体を上下左右いずれかにごくわずかにずらした構図
- 日の丸構図よりもこなれた印象になる
2.三分割構図

- 画面を縦に三分割、横に三分割し、交点のいずれかに被写体を配置する構図。交点には被写体の中で一番の注目ポイントである、「顔」となる部分を置くのが基本
- 画面全体のバランスが良くなり、安定感が生まれる
- 鑑賞者の視線を誘導し、画面全体を鑑賞してもらいやすい
★撮影画面にグリッド線を表示すると、目安にしながら撮影できます。
五分割構図
- 画面の端にメインの被写体や地平線・水平線を大胆に寄せる構図
- 三分割よりもたっぷり余白が生まれて爽快な感じに仕上げやすく、僕自身、多用している構図です
- 必ずしも厳密に五分割した枠線を意識する必要はなく、六分割程度でもOK
3.対角線構図

- 画面の対角線上に被写体が並んだ構図
- 変化がついてダイナミックな印象を与えたり、奥や手前をぼかすことで空間に奥行きを感じさせたりすることができる
- 木の枝や橋のように、被写体の中に線を見つけて対角線になるように配置する。また、複数の被写体を斜めになるように配置することでも構図を作ることができる。
■フレーミング
どの要素を入れ、どの要素を入れないか、写真に映す範囲を決定すること。
フレーミングを意識しならがら構図を決めると、より被写体が引き立ちバランスの良い写真に近づけることができます。
フレーミングのポイント
まずは一番に伝えたい、メインの被写体を決めます。
次に、メインの被写体より目立ったり、邪魔になるようなものをフレームの外に出します。例えば、メインの被写体よりもビビッドな色合いのものだったり、つい読んでしまうような看板の文字などは得てして悪目立ちして主役の被写体が入ってこなくなるから要注意!
最初は引きでフレーミングして、徐々に被写体に寄りながらフレームに残したいものと、入れたくないものを選別するのがおすすめです。
Adviser's Note




Z 50 NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
左上から)日の丸ずらし構図/対角線構図/三分割構図/五分割構図
恐らくどの写真の教科書にも載っていなくて邪道に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、日の丸ずらしと五分割構図はよく使います。人物の顔などを画面の中心に置くと「ザ・日の丸構図」になってしまい、初心者っぽさが際立ってしまいますが、これを少しだけずらすだけで日の丸感が薄れるのです。測距点(AFフレーム)を動かさずに、中央のポイントを使えばいいので挑戦もしやすいですよ。
五分割構図は必ずしも厳密に五分割した枠線を意識する必要はなく、6分割くらいでも大丈夫。要は、画面のすみっこにメインの被写体や地平線・水平線を大胆に寄せればOKです。三分割よりもたっぷり余白が生まれて爽快な感じに仕上げやすく、僕自身、多用している構図です。
第6回は……
おいしくてかわいいパンケーキが評判のカフェに、カメラを持って訪れたミナちゃん。せっかくのパンケーキを素敵に撮ることが目標です! すると、隣の席にミナちゃんと同じようにカメラを持った女の子が。彼女はフォトグラファーのmisuzuさん。おしゃべりしながら、食べ物のおいしい瞬間を切り取るコツを教えてもらいます。
illust:冨田マリー(@tomitamary_)
Supported by 東京通信社

嵐田大志
スマートフォンのアプリを活用し、フィルム風の空気感を表現。家族や身近なものを中心にしつつ、頻繁に旅する海外でのスナップを撮り続けている著書に『デジタルでフィルムを再現したい』(玄光社)






