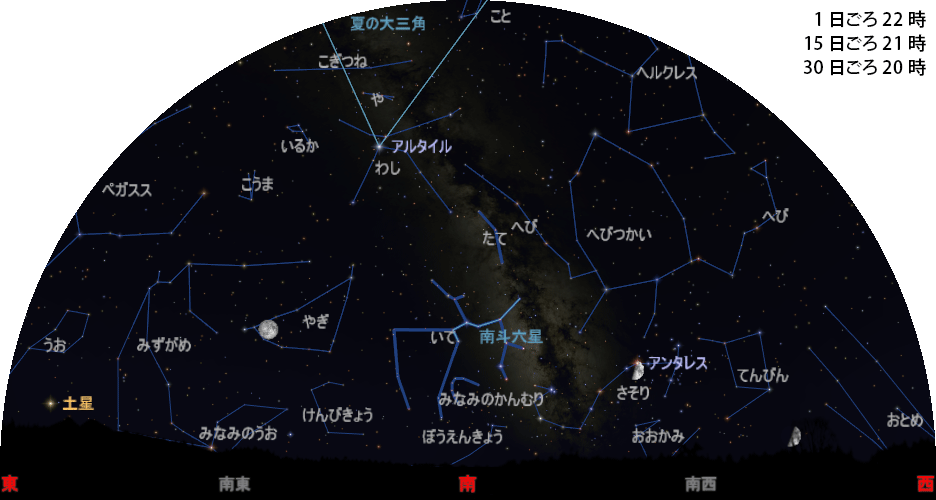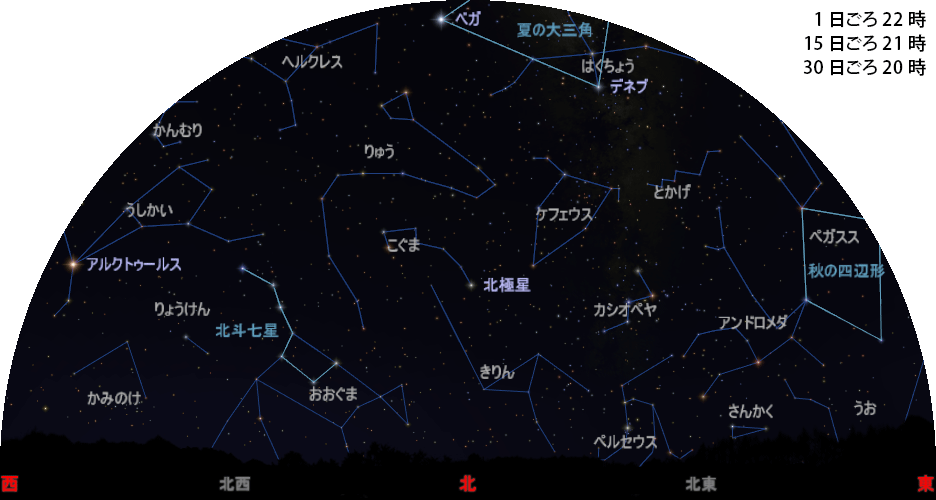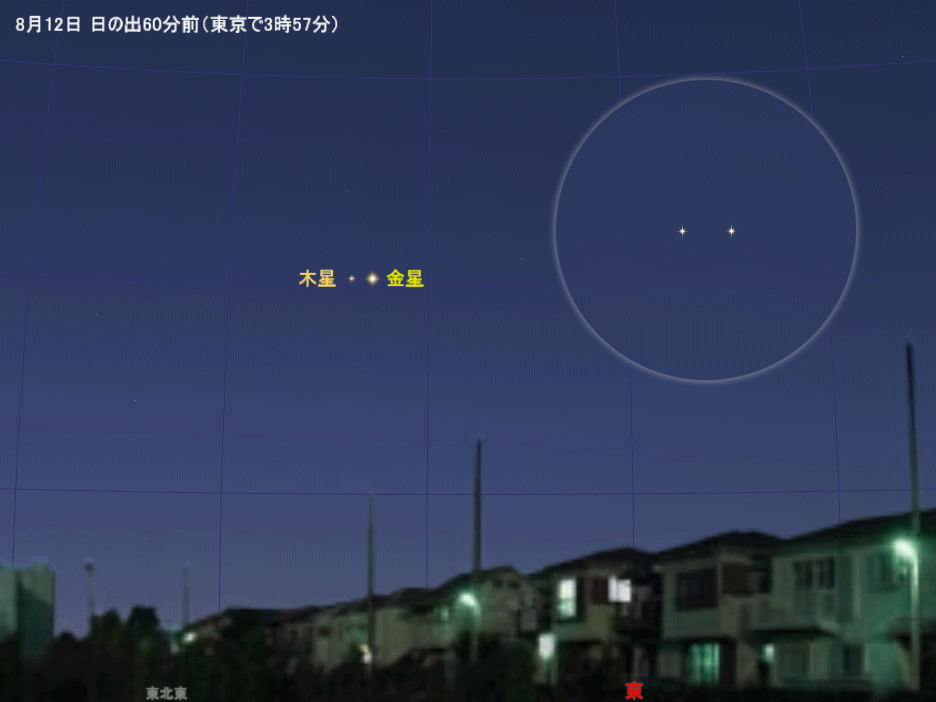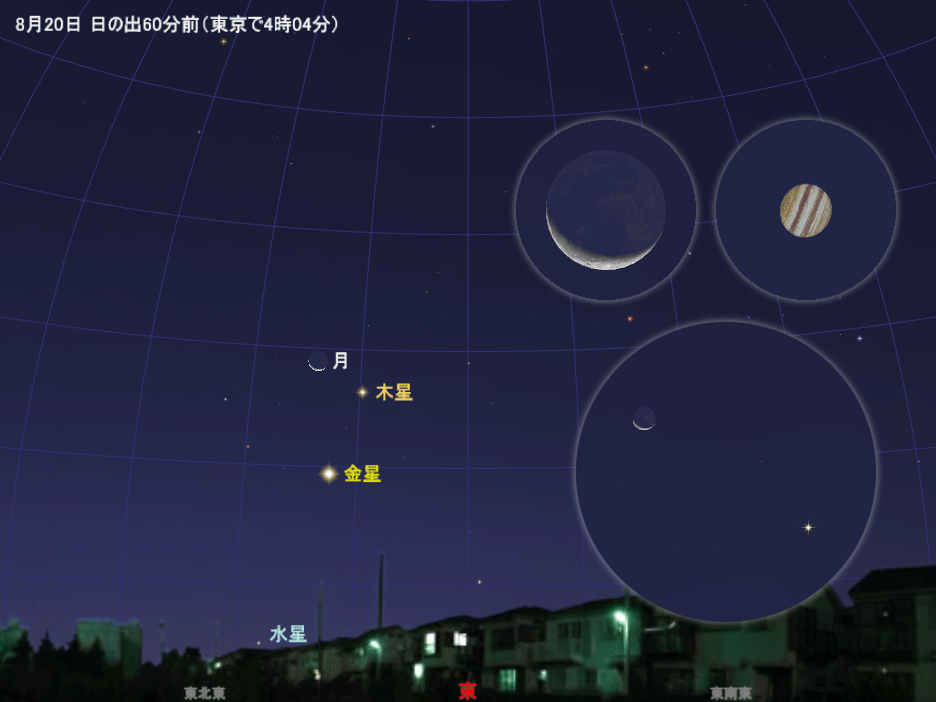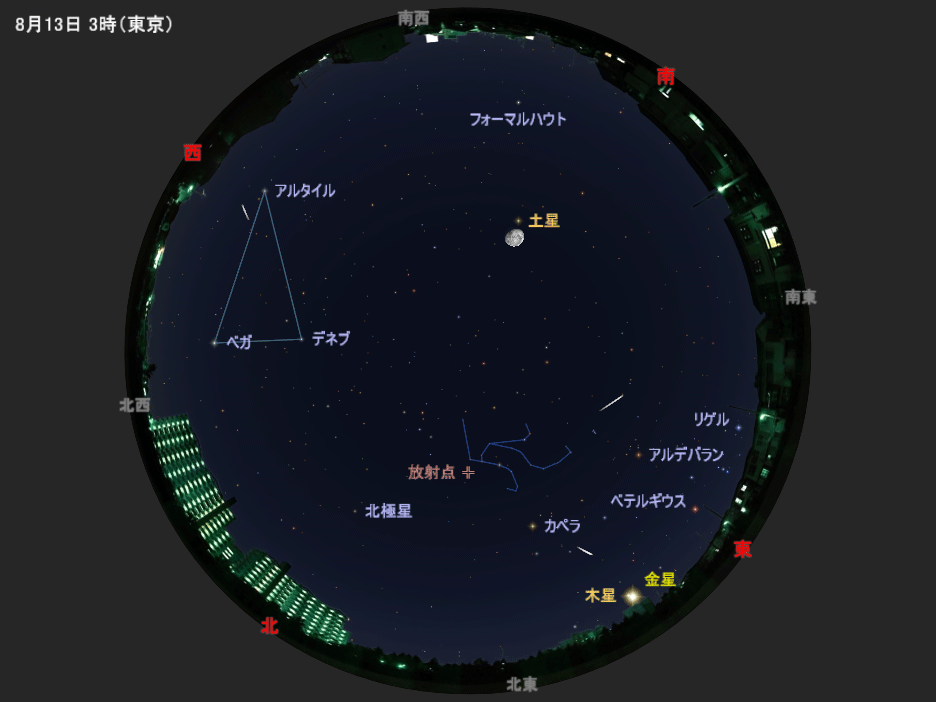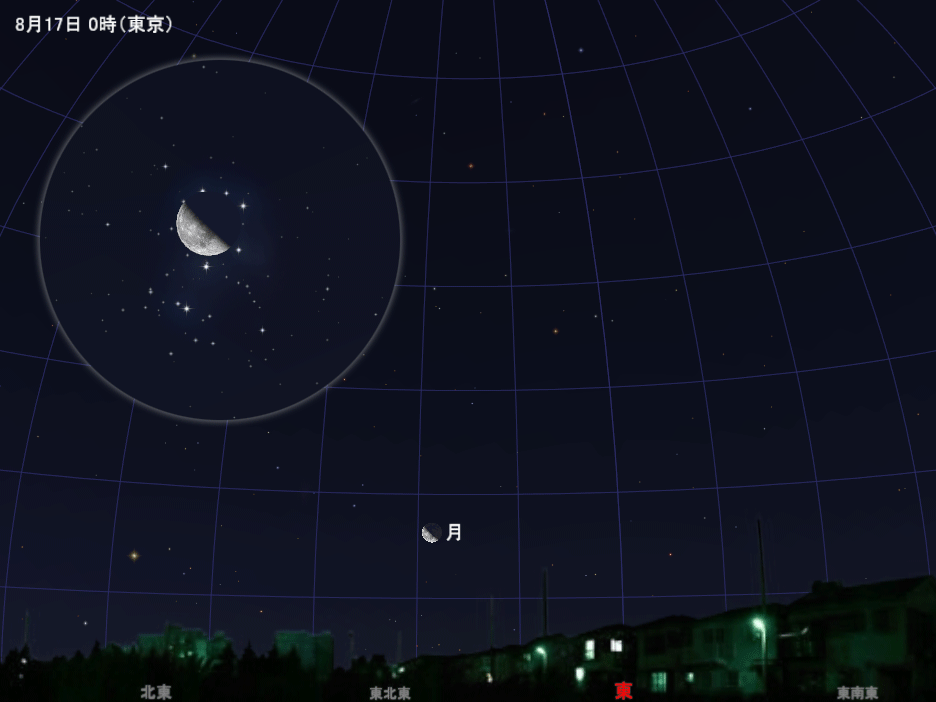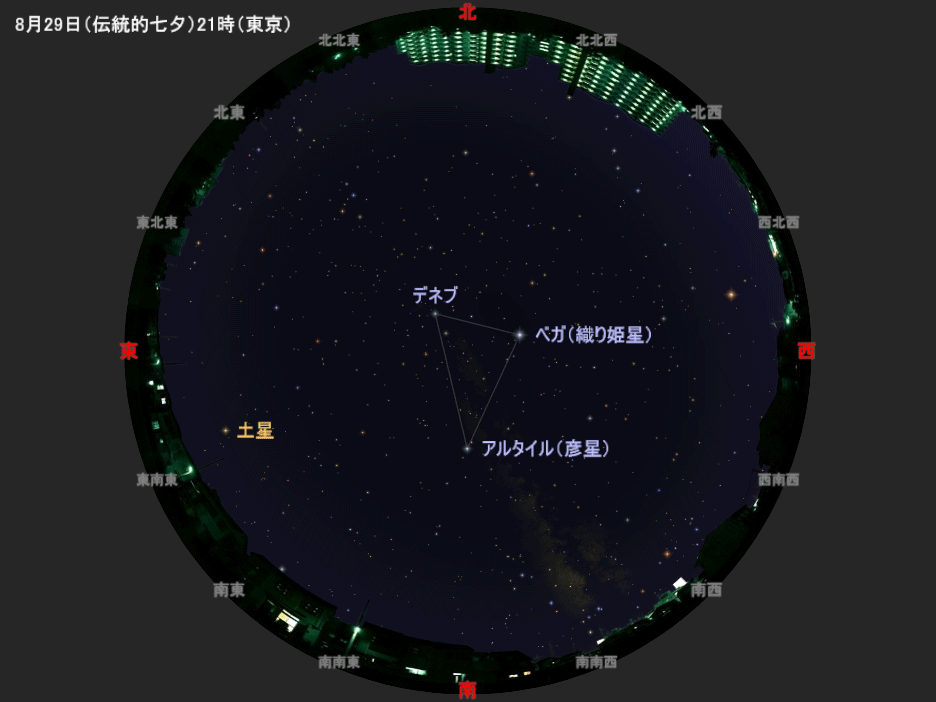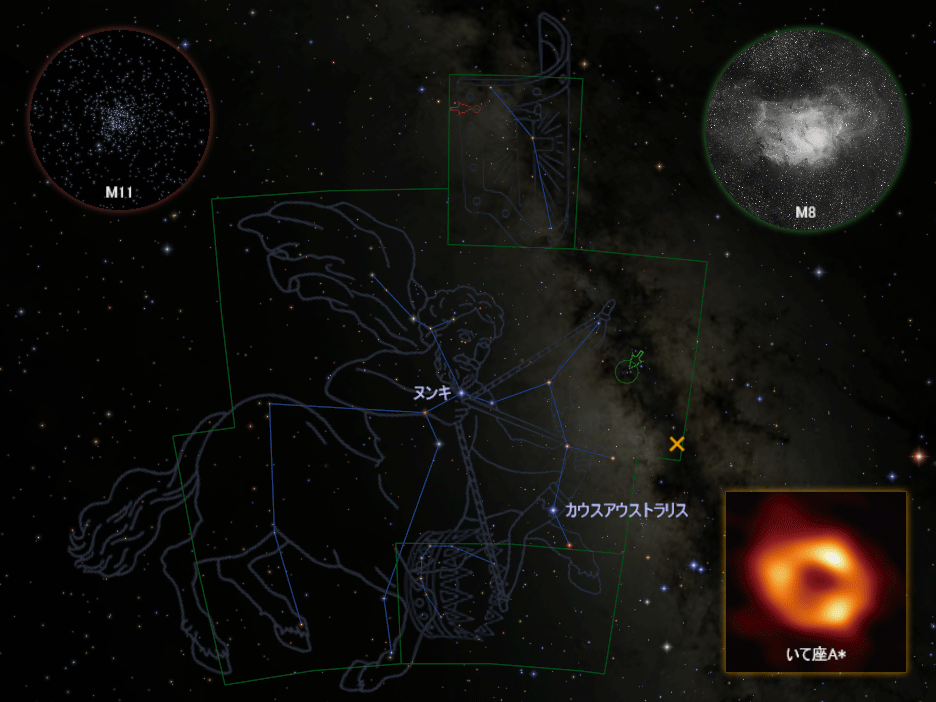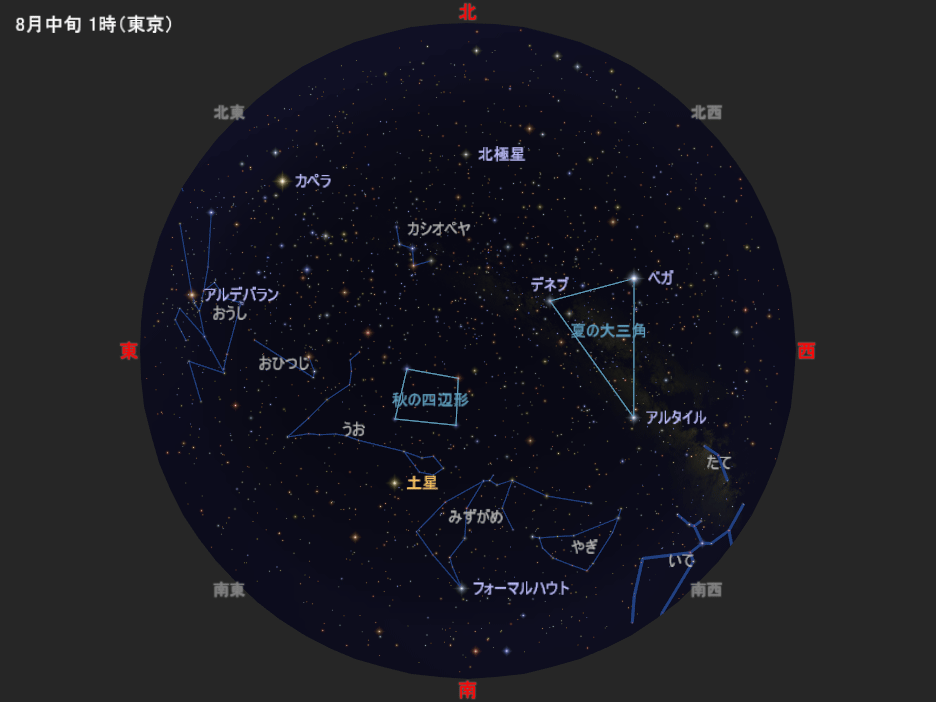2025年8月の星空
ペルセウス座流星群、金星と木星の大接近、プレアデス星団の食など、今月は未明から明け方に注目の現象が目白押しです。夜にも暑さは残りそうですが、星々を見上げれば少しは涼を感じられるでしょう。旅行先や帰省先、普段とは違う場所からの空も眺めてみてください。
群馬県・長野県 渋峠(群馬県側)にて
巻雲が星空の6割以上を占める状況でしたが、プレアデス星団とヒヤデス星団を撮影していたところに流星が飛び込んでくれました。小ぶりではあるものの、流星が入ることでアクセントが生まれ、エモーショナルな表現になったように思います。
2021年8月6日 2時47分
ニコン Z6II+NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S(35mm、ISO12800、露出5秒、f/2.8)
撮影者:高岡 誠一
8月の星空
天文カレンダー
1日(金) |
上弦(日没ごろに南の空に見え、夜半ごろ西の空に沈む) |
| 3日(日) |
深夜、月とアンタレスが並ぶ |
| 4日(月) |
夕方~深夜、月とアンタレスが接近 |
| 7日(木) |
立秋(こよみの上で秋の始まり) |
9日(土) |
満月。次の満月は9月8日です |
| 12日(火) |
このころ、未明~明け方に金星と木星が大接近(「今月の星さがし」で解説)
宵~翌13日明け方、月と土星が接近 |
| 13日(水) |
ペルセウス座流星群の活動がピーク(「今月の星さがし」で解説) |
16日(土) |
下弦(夜半に東の空から昇り、明け方に南の空に見える。下弦~新月は夜空が暗く、星が見やすくなります)
23時~翌17日2時ごろ、プレアデス星団食(星団の星々が月に隠されます。「今月の星さがし」で解説) |
| 19日(火) |
水星が西方最大離角(明け方の東北東の低空に見えます) |
| 20日(水) |
未明~明け方、細い月と木星が接近(「今月の星さがし」で解説)
未明~明け方、細い月と金星がやや離れて並ぶ |
| 21日(木) |
未明~明け方、細い月と金星が並ぶ(「今月の星さがし」で解説)
未明~明け方、細い月とポルックスが並ぶ |
| 22日(金) |
明け方、細い月と水星が接近(「今月の星さがし」で解説) |
23日(土) |
新月(下弦~新月は夜空が暗く、星が見やすくなります) |
| 27日(水) |
夕方~宵、細い月とスピカが接近 |
| 29日(金) |
伝統的七夕(「今月の星さがし」で解説) |
31日(日) |
上弦(日没ごろに南の空に見え、夜半ごろ西の空に沈む)
夕方~宵、月とアンタレスが大接近 |
8月の惑星
13日ごろから、明け方の東北東の低空に見えます。
日の出30分前(東京で4時30分ごろ)の高度は10度前後あり、太陽から大きく離れることがない水星としては見やすい条件です。同じ夜明け空に見える金星と木星を目印にすると、水星の位置がわかりやすいでしょう。肉眼でも見える明るさですが、双眼鏡を使うと見やすくなります。低空まで見晴らしの良い場所で探しましょう。
22日の明け方、月齢28の極細の月と接近します。「今月の星さがし」も参考にしてください。
「明けの明星」として、未明から明け方の東の空に見えます。
日の出1時間前(東京で4時ごろ)の高度は約20度でやや低めですが、とても明るいので簡単に見つかります。
12日ごろに木星と大接近します。明るい2天体が寄り添って輝く光景は見もので、ぜひ早起きして観察したい現象です。「今月の星さがし」を参考にしてお楽しみください。
20日の未明から明け方、月齢26の細い月とやや離れて並びます。また、翌21日の未明から明け方にも、月齢27の細い月と並びます。
「おとめ座」にあり、日の入りの約2時間後(東京で20時30分ごろ)に沈みます。明るさは約1.6等級です。
低く、火星としては暗いので、観察には向いていません。
「ふたご座」にあります。2時ごろに昇ってきて、日の出1時間前(東京で4時ごろ)に東北東から東の低空に見えます。明るさは約マイナス1.9等級です。
あまり高くはありませんが、明るいのでよく目立ちます。また、さらに明るい金星が近くに輝いているので、夜明けの東天は壮観です。木星と金星は12日ごろに最接近し、前後数日間がとくに見ものです。早起きして眺めましょう。「今月の星さがし」の星図もご覧ください。
20日の未明から明け方、月齢26の細い月と接近します。
「うお座」にあります。20時ごろに昇ってきて、0時ごろに南東の空、2時ごろに真南の空に見えます。明るさは約0.7等級です。
高度が上がってきたおかげで、そろそろ天体望遠鏡での観察もしやすくなってきました。今シーズンは環の傾きが小さく、そのため環が見づらいのですが、このような姿は約15年ごとにしか見られない珍しいものです。見慣れない姿を観察できるチャンスは来年2月ごろまでありますが、機会があるたびに確認しておきましょう。
12日の宵から13日の明け方にかけて、月齢19の満月過ぎの月と接近します。
今月の星さがし
ペルセウス座流星群の見ごろは12~13日にかけて。月明かりがあっても見逃せません。同じころには明け方の空で金星と木星が大接近し、16~17日には今年2回目のプレアデス星団食も起こります。体調とスケジュールをしっかり管理して楽しみたいものです。
明けの明星と木星
春から「明けの明星」として夜明け前の東天で眩しく輝いている金星は、今月も存在感があります。その金星の近くにも、目を引く明るい星があります。こちらは木星です。月と一部の人工衛星を除けば、夜空で最も明るく見えるのが金星、2番目が(平均的には)木星なので、両者が並ぶ様子はひときわ目立ちます。
金星と木星の間隔は日々変化し、12日ごろに最接近して見えます(13日もほぼ同じ間隔です)。満月2個分ほどの幅という大接近で、見ごたえ満点です。上の星図では日の出60分前の様子を示していますが、日の出30分前くらいの空の明るさでも見ることができるでしょう。反対にもっと早い時間帯でも、視界が開けていれば見られます。2つの惑星のそばに鉄塔の先端や山の頂上などが見える場所を選ぶと、面白い光景を見たり撮ったりできるかもしれません。ぜひ早起きしてご覧ください。
20日と21日には、間隔が開いた木星と金星の近くに細い月が並びます。この光景も暑さをしばし忘れさせてくれるような美しいものですので、眺めてみたいですね。22日には、金星のさらに下のほうで光っている水星の隣に新月前のとても細い月が接近します。見晴らしの良い場所で探してみましょう。
12~13日、ペルセウス座流星群の活動がピーク
毎年8月13日ごろに活動がピークとなるペルセウス座流星群は、夏の定番の天文現象です。条件が良ければ1時間あたり数十個の流れ星が見られる、一年のうちでも指折りのおすすめ流星群です。夏休みシーズンであることや、寒くないので見やすいこと、毎年安定して活動が見られることも嬉しいポイントです。速く明るい流星が多いおかげで見応えがあり、流れ星が飛んだあとに煙のような「流星痕」が見えることもあります。
今年ペルセウス座流星群の活動が最も活発になるのは13日明け方5時ごろと予想されていますので、12日深夜から13日明け方にかけての夜が一番の見ごろになります。明け方になるほどピーク時刻に近づき、放射点(流れ星が飛ぶ中心点)が高くなって数が増えるという効果も加わって、いっそう見やすくなるでしょう。
ただし、惜しいことに今年は明るい月明かりが一晩中、夜空を照らします。そのため、暗い流星は見えなくなってしまうので、目にできる流星数は少なくなってしまいそうです。先述のとおり明るい流星が多いので、月明かりや街明かりに負けないほどの大流星が現れることに期待しましょう。
流れ星観察の重要なポイントは、空を広く見渡すことです。流れ星はペルセウス座の方向だけでなく、空のあちこちに飛ぶので、なるべく広い範囲を眺めましょう。広く見ることが大切ですから、双眼鏡や天体望遠鏡は不要です。今年の場合は月の方向は避けて、また郊外で観察する場合には街灯などを目に入れないようにすると見やすくなります。
1時間に20個見えるとすると平均では約3分に1個見えることになりますが、流れるペースは不規則なので、立て続けに数個見えることもあれば10分近くも流れ星を目にできない可能性もあります。虫よけを準備して、安全やマナーに気をつけながら、ゆったりと空を見上げてみてください。
「月の方向は避けて」と説明しましたが、実はこの夜は月と土星が接近している光景も見られます。また、夜明けが近くなってくると、金星と木星が寄り添う様子も東の低空に見えます。ペルセウス座流星群以外にも楽しみの多い夜ですね。好天に恵まれて、全部ご覧になれますように。
16日深夜~17日未明 プレアデス星団の食
16日の23時ごろから17日の2時ごろにかけて、下弦の月が「おうし座」のプレアデス星団(すばる)の手前を通り過ぎて星々を隠す「プレアデス星団食(すばる食)」が起こります。3月5日以来、今年2回目のプレアデス星団食です。
プレアデス星団は肉眼でも見える明るい天体ですが、今回のように月が近いときには月の光に埋もれてしまい、肉眼ではとても見づらくなります。双眼鏡や、低倍率の天体望遠鏡で観察しましょう。また、低空で起こる現象のため、東北東から東の空が地平線までよく開けている場所を見つけておきましょう。
今回は月の縁の明るいほうから星が隠れ、暗いほう(欠けている部分)の縁から星が現れます。隠されていた星が急にパッと見えるのは面白い体験です。シミュレーションソフトを使えば、どの星がどこから隠れて現れるか、秒の単位で正確にわかりますが、細かいことは気にせずに「星が次々に隠れては現れる」のを眺めるだけでも楽しいものです。
深夜から未明の時間帯ですが、ちょうど土日なので夜更かししやすいという方も多いでしょう。星団の星々を背景に月が浮かんでいる光景を、ぜひご覧ください。
29日は伝統的七夕
七夕は古くからの行事で、もともとは旧暦の7月7日に行われていました。そこで、この旧暦7月7日(※)を「伝統的七夕」と呼び、天文行事として親しまれています。伝統的七夕の日は毎年日付が変わり、今年の場合は8月29日とずいぶん遅めです。
※旧暦は現在公的には使われていないため、伝統的七夕の日は「太陽太陰暦と同じような方法で求めた7月7日に近い日」として、太陽の位置や月の満ち欠けをもとにして決められます。
今年は梅雨明けが早い地方が多かったものの、例年であれば7月7日は多くの地域で梅雨の真っ最中です。そのため、7月7日の夜空には織り姫星(「こと座」のベガ)と彦星(「わし座」のアルタイル)が見えないことも少なくありません。伝統的七夕のころには梅雨も明けているので、晴れた夜空が見られる確率が高くなります。また、旧暦では1日が新月なので、その6日後となる旧暦7日は必ず上弦の月のころになります。南西の空に見える半月が沈むと、空が暗いところではベガとアルタイルの間に天の川も見えるでしょう。
7月7日の七夕にはイベント的な楽しみや宇宙に親しむきっかけとしての意味合いがあり、伝統的七夕には古くからの人と宇宙のつながりを感じたり暗い星空に思いを馳せたりという良さがあります。伝統的七夕の夜にもぜひ、織り姫星と彦星を見上げてみてください。
今月の星座
いて座
11月下旬から12月中旬ごろに誕生日を迎える人の星座として名前が知られている「いて座」、宵空で見やすいのは8月ごろです。8月中旬の21時ごろ、南の空のやや低いところに見えます。
「いて座」の目印は2等星のカウスアウストラリスとヌンキです。どちらも明るい星ですが、日本から見るとあまり高くならないので、街明かりの影響などでそれほど目立ちません。条件の良いところで観察しましょう。
より暗い星まで見えれば、ヌンキのあたりに並ぶ北斗七星に似た星々がわかります。南の空にあって星の数が6つなので「南斗六星」と呼ばれます。また、もっと広い範囲の星々をつないで「ティーポット」に見立てることもあります。街明かり、月明かりがなければ、ティーポットの注ぎ口から湯気のように立ちのぼる天の川も見えるでしょう。星図(アニメーション画像)を参考にして、南斗六星やティーポットの星々、天の川を観察してみてください。
ギリシャ神話では半人半馬のケンタウルス族のケイロン、またはフォロスとされることが多いようです。弓矢を引き絞って狙う先に「さそり座」がありますが、神話上のつながりはとくにありません。
みなみのかんむり座、たて座
「いて座」の足元には半円形に星が並ぶ「みなみのかんむり座」があります。また、南斗六星の上のほう、天の川の流れの中には「たて座」があります。
どちらも明るい星がないので、見つけるのはやや難しいのですが、「いて座」を観察するときには「みなみのかんむり座」と「たて座」も少し意識してみましょう。
天の川の中の星雲、星団
「いて座」「たて座」のあたりは天の川が最も濃くなっているところで、双眼鏡で眺めると視野いっぱいに星が広がります。そのなかでも部分的に星が集中している天体は「星団」と呼ばれ、天の川沿いに点在しています。「たて座」の星団M11(Mはカタログの符号)は星がコンパクトに集まり、小型の天体望遠鏡でも美しい眺めが楽しめます。鳥が群れている様子にたとえて「野鴨星団」と呼ばれることもあります。
また、このエリアには星団だけでなく、宇宙空間に漂うガスや塵が光って見える「星雲」もたくさんあります。南斗六星の柄にあたる星の近くに見える「干潟星雲」M8は比較的明るく、空の条件が良ければ双眼鏡でもガスの広がりが確認できます。このほか「三裂星雲」M20や「オメガ星雲」M17なども有名で、天体写真撮影の人気のターゲットにもなっています。
天の川銀河の中心
星図中「×」のところは、天の川銀河(銀河系)の中心方向です。天の川銀河は数千億個の星が円盤状に集まった天体で、太陽(太陽系)はその中心から約2万7000光年離れた円盤内にあります。中心方向はやや膨らんでおり、星も多いので、とくにこの方向の天の川が濃く太く見えるのです。この方向には黒い部分も多く見られますが、ここはガスや塵で星の光が遮られているところです。
天の川銀河の中心には、太陽の約400万倍もの質量を持つ超大質量ブラックホール「いて座A*(エースター)」が存在すると考えられています。2022年にそのブラックホールが作る「シャドウ(影)」の画像(色は擬似的なものです)が公開され、話題となりました。「いて座」を眺めるときには、天の川銀河全体や、天文学研究の最先端にも想像を巡らせてみてください。
真夜中の星空
夜遅く帰ってくる人のため、ちょっと夜更かしの人のため、真夜中の星空をご案内しましょう。
図は8月中旬の深夜1時ごろの星空です。9月中旬の深夜23時ごろ、10月中旬の夜21時ごろにも、この星空と同じ星の配置になります(惑星は少し動きます/月が見えることもあります)。
「夏の大三角」が西の空の高いところに見えます。伝統的七夕の日に限らず、織り姫星ベガと彦星アルタイル、間を流れる天の川を仰ぎましょう。とくに願いをかけなくても、星空を見上げることは気持ちの良いものです。
頭の真上あたりには「秋の四辺形」が広がり、天馬「ペガスス座」が駆けています。大きな翼で深夜の暑気を払ってほしいものですね。暑くて眠れなければ、南の空の土星を観察したり、流れ星を待ったりしてみましょう。
もう少し夜更かしすると、東の空に金星と木星が並んで昇ってきます。美しい共演はぜひ眺めたいものですが、睡眠不足にならないようにお気をつけて。
星空観察と撮影のポイント
星座や惑星、流星群などの天文現象の観察や撮影は、コツを抑えるとただ眺めるよりも広く深く楽しむことができます。
ここでは、天体の探し方からおすすめの撮影機材やテクニックまで、星空を楽しむうえで知っておきたいポイントをご紹介します。
カメラや双眼鏡を持って、美しい夜空に会いにいきましょう!
星空観察と撮影のポイント