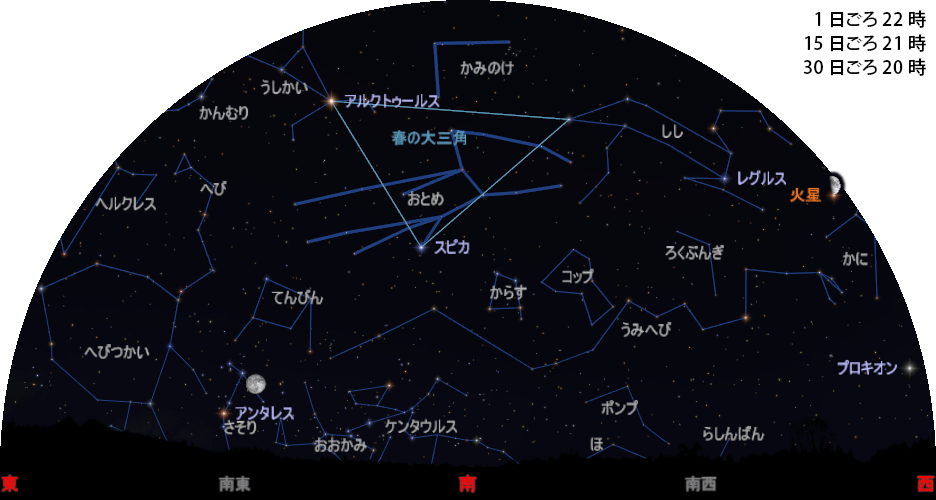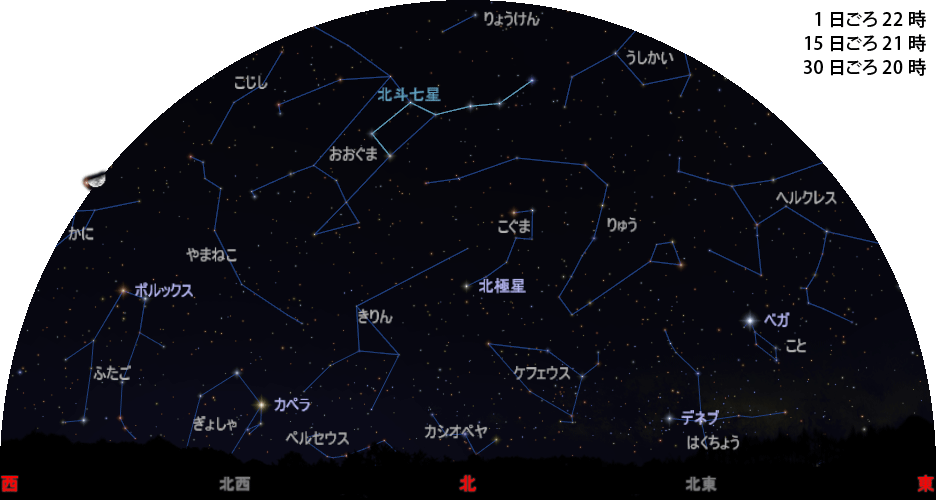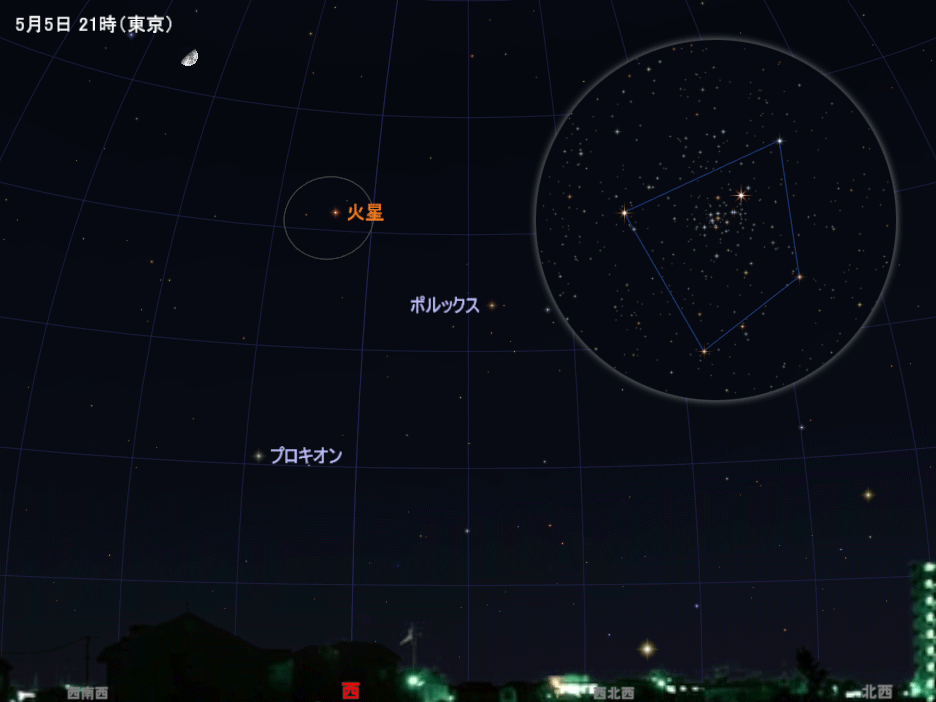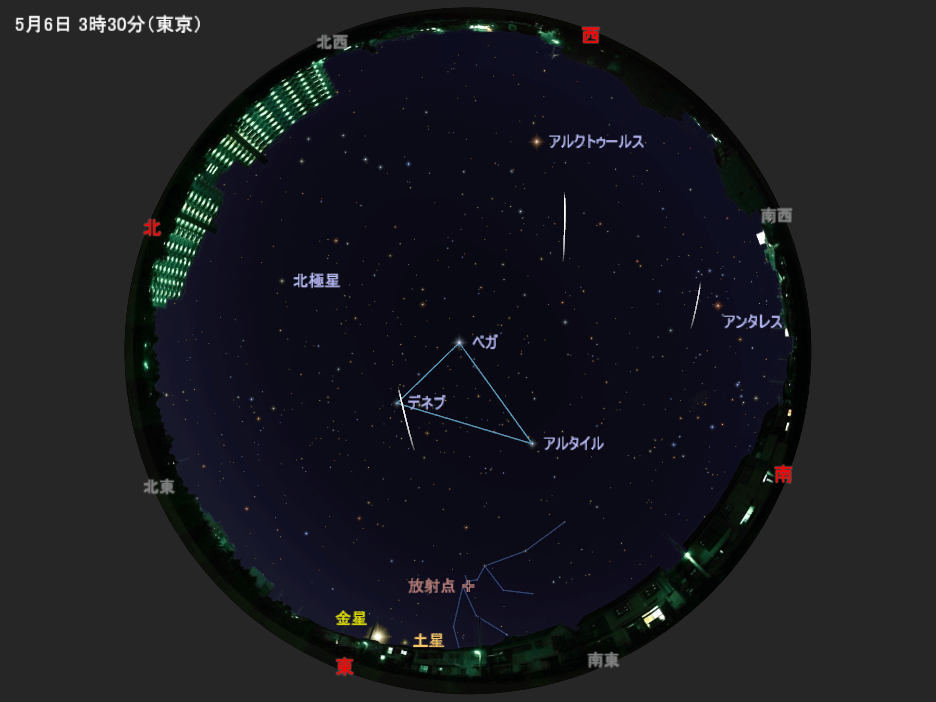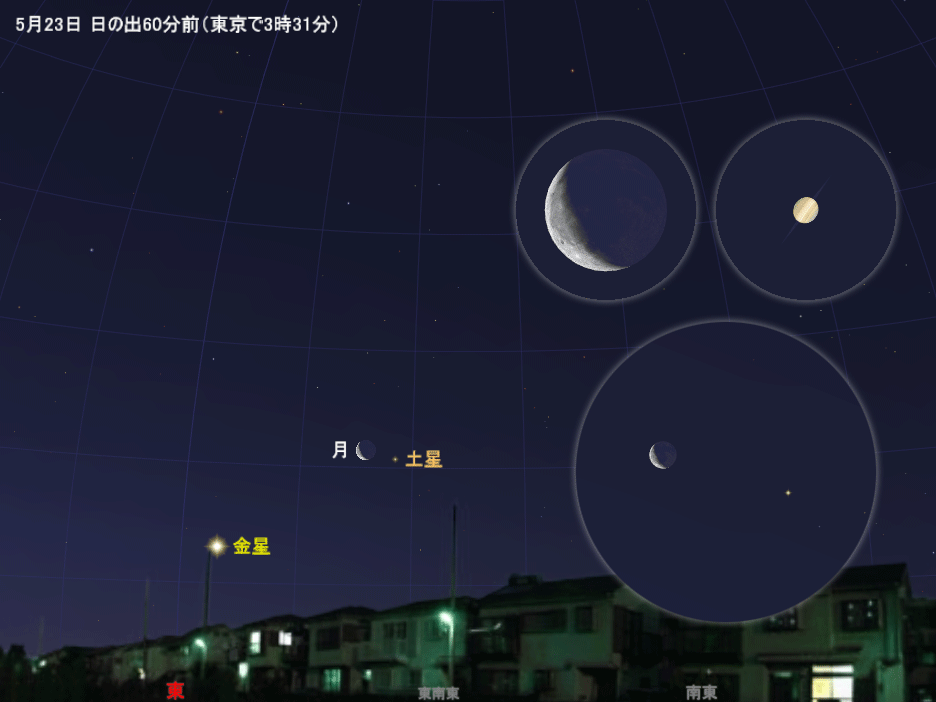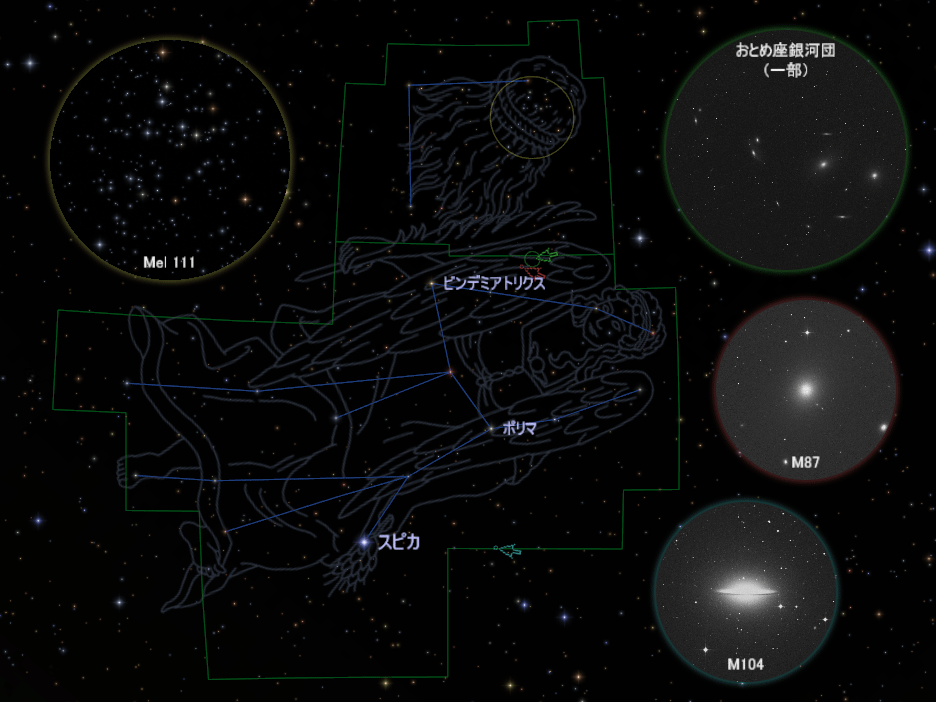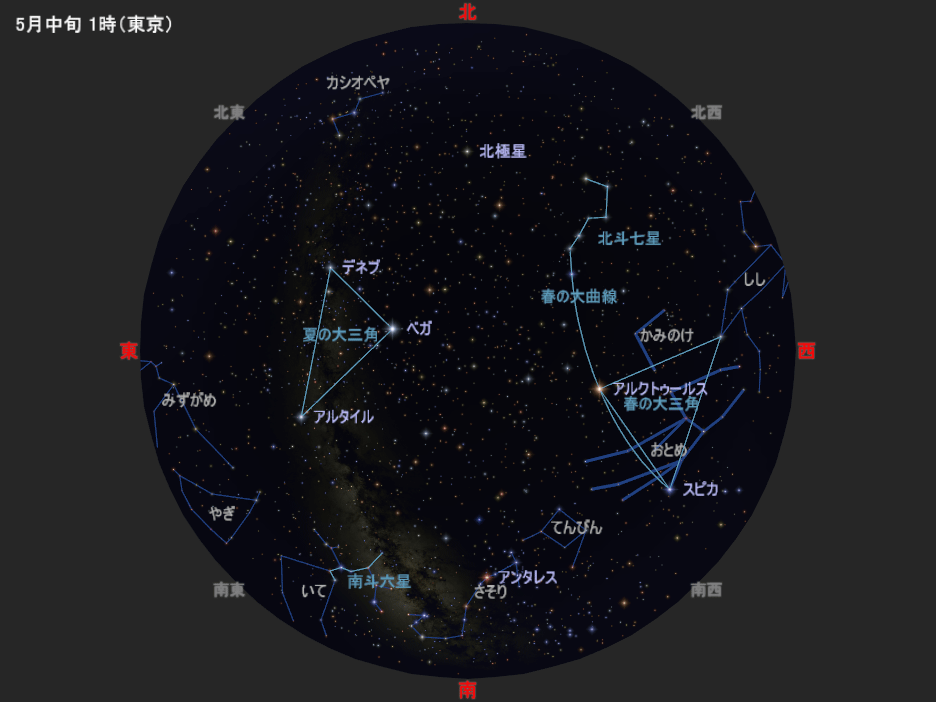2025年5月の星空
西の空に見えるかに座の中を、火星が横断していきます。プレセペ星団と火星の共演を双眼鏡で観察しましょう。月末には明け方の空で、細い月と金星の接近も楽しめます。星座探しではおとめ座の、全天2位の大きさを確かめてみましょう。
愛知県新城市にて
新城市のミツマタの群生地に行ってきました。深夜で近くに街灯もなく真っ暗な静寂の中、満開のミツマタの上に、かわいらしいからす座と1等星のスピカを擁するおとめ座が昇ってきました。冬の終わりと春の訪れを感じさせてくれる撮影になりました。
2024年3月15日 0時04分
ニコン Z6II+NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S(14mm、ISO8000、露出15秒×16枚を合成、f/2.8)
撮影者:石橋 直樹
5月の星空
天文カレンダー
| 2日(金) |
深夜、月とポルックスが並ぶ |
| 3日(土) |
夕方~宵、月とポルックスが並ぶ
深夜、月と火星が並ぶ |
4日(日) |
上弦(日没ごろに南の空に見え、夜半ごろ西の空に沈む)
夕方~深夜、月と火星、プレセペ星団が並ぶ |
| 5日(月) |
立夏(こよみの上で夏の始まり)
このころ、夕方~深夜に火星とプレセペ星団が大接近(「今月の星さがし」で解説)
夕方~翌6日未明、月とレグルスが接近 |
| 6日(火) |
みずがめ座η流星群の活動がピーク(「今月の星さがし」で解説) |
| 7日(水) |
土星の環の消失(土星の環が見づらい状態が続いています) |
| 10日(土) |
夕方~翌11日未明、月とスピカが大接近 |
13日(火) |
満月。次の満月は6月11日です
深夜~翌14日明け方、月とアンタレスが並ぶ |
| 14日(水) |
宵~翌15日明け方、月とアンタレスが接近 |
20日(火) |
下弦(夜半に東の空から昇り、明け方に南の空に見える。下弦~新月は夜空が暗く、星が見やすくなります) |
| 23日(金) |
未明~明け方、月と土星が接近(「今月の星さがし」で解説) |
| 24日(土) |
未明~明け方、細い月と金星が接近(「今月の星さがし」で解説) |
27日(火) |
新月(下弦~新月は夜空が暗く、星が見やすくなります) |
| 28日(水) |
夕方、細い月と木星が並ぶ |
| 30日(金) |
夕方~宵、細い月とポルックスが並ぶ |
| 31日(土) |
夕方~深夜、細い月とプレセペ星団が大接近 |
5月の惑星
中旬まで明け方の東の低空に見えますが、日の出30分前(東京で4時10分ごろ)の高度は5度未満と非常に低いので、観察は困難です。
「明けの明星」として、未明から明け方の東の低空に見えます。
日の出45分前(東京で3時50分ごろ)の高度は約15度と低めですが、とても明るいおかげで、建物などに隠されていなければ簡単に見つかります。東の空が地平線近くまでよく見渡せるところで観察しましょう。
5日ごろまで土星と接近して見えます。また、24日には月齢26の細い月と接近します。「今月の星さがし」を参考にして、美しい共演をお楽しみください。
「かに座」を横断し、下旬に「しし座」に移ります。20時ごろに西の空に見え、日付が変わるころに沈みます。明るさは約1.1等級です。
とても目立つというほどではありませんが、依然として1等級と明るく、赤っぽい特徴的な色が目を引きます。今月は何と言っても、連休のころに「かに座」のプレセペ星団に大接近する現象が楽しみです。「今月の星さがし」を参考にして、双眼鏡で観察しましょう。
3日の深夜に月齢6の月と並びます。また、翌4日の夕方から深夜にも月齢7の上弦の月と並びます。
夕方の西北西の低空に見え、21時ごろに沈みます。明るさは約マイナス1.9等級です。
今シーズンの観望はそろそろ終わりで、来月には太陽に近づいて見えなくなります。今月中に見納めしておきましょう。
28日の夕方、月齢1の極細の月と並びます。
明け方の東南東の低空に見えます。明るさは約1.1等級です。
日の出45分前(東京で3時50分ごろ)の高度は約20度と低めです。近くに金星が輝いているので、これを目印にすると見つけやすいでしょう。低いので天体望遠鏡での観察には向いていませんが、拡大すると「環がほとんど見えない」状態であることがわかるかもしれません。
5日ごろまで金星と接近して見えます。また、23日には月齢25の細い月と接近します。
今月の星さがし
ゴールデンウィークのころ、火星が「かに座」のプレセペ星団に大接近します。双眼鏡で美しい光景を観察できそうです。明け方の空に見えている金星と土星には、月末に細い月が寄り添います。
火星がプレセペ星団に大接近
先月中旬に「ふたご座」から「かに座」の領域に移った火星は、今月その「かに座」を西から東へと横切っていき、その途中で「かに座」の中央付近に広がる星の集団、「プレセペ星団」と大接近します。最も近づいて見えるのは5日ごろです。
空の条件が良いところなら肉眼でも見えますが、おすすめは双眼鏡での観察です。星々と火星の明るさや色の違いがわかりやすくなり、美しい眺めをより楽しめます。郊外でも、見える星の数は減りますが共演はよく見えるので、双眼鏡を火星に向けてみましょう。天体の並び方の変化にも注目してみてください。
6日未明~明け方、みずがめ座η流星群
みずがめ座η(エータ、イータ)流星群は、毎年ゴールデンウィークの終盤に活動がピークとなる流星群です。「みずがめ座」のη星付近を中心として四方八方に流れ星が飛ぶように見えることから、このような名前で呼ばれています。
今年は6日の12時ごろに計算上のピークを迎えると予想されています。これは昼の時間帯なので、実際には6日の未明から明け方が一番の見ごろということになります。流れ星が飛ぶ中心となる「放射点」が地平線上に昇る1時30分ごろから、空が明るくなる4時前ごろまでが、観察に適した時間帯です。月明かりの影響を受けず、好条件で観察できます。
放射点や「みずがめ座」は東の低空にありますが、流れ星は空のどの方向、どの高さにも飛ぶ可能性があるので、なるべく広く空を見渡しましょう。東の空の流星は下から上に、南の空を向けば左から右に、西の空の高いところでは上から下に飛ぶように見えます。星図(円周が地平線、中心が頭の真上にあたります)で方向をイメージしてみてください。
有名な流星群と比べると数は少なめですが、1時間あたり10個ほどは流れ星が見られると予想されます。連休最終日ですが、早起きしてお楽しみください。
23日と24日、細い月と土星、金星が接近
夜明け前の東の低空には、「明けの明星」の金星が眩しく輝いています。また、金星の右のほうには土星もあります。金星ほど明るくはないものの、肉眼でも見つけられる明るさです。
23日と24日に、この2つの惑星の近くに細い月がやってきます。肉眼で広く眺める、双眼鏡で接近の様子を観察する、地上風景を入れて撮影してみるなど、いろいろな手段で楽しめそうです。
天体望遠鏡で観察すると、金星が半月状に見えること、土星の環がほとんど見えないことなどもわかるかもしれません。明け方という時間帯や低空という条件のため、望遠鏡での観察はやや難しいのですが、お持ちであれば挑戦してみてはいかがでしょうか。
今月の星座
おとめ座
8月下旬から9月中旬ごろに誕生日を迎える人の星座として名前が知られている「おとめ座」、宵空で見やすいのは5月ごろです。5月中旬の20時から21時ごろ、南の空に大きく広がっています。
「おとめ座」の目印は青白く輝く1等星スピカです。スピカは「うしかい座」のアルクトゥールス、「しし座」のデネボラと合わせて「春の大三角」を構成する星で、南の空に三角形があるときには一番低いところに見えます。この春の大三角の内側に「おとめ座」が大きく広がっています。
スピカの名前は「麦の穂」という意味の語に由来し、星座絵ではその由来どおりに女神が左手に持った麦穂の位置に輝いています。ギリシャ神話における農業の女神デーメーテールが「おとめ座」のモデルとされているので、麦を持っているのも納得ですね。別の説ではデーメーテールの娘ペルセポネーや、正義の女神アストライアーともされます。
「おとめ座」は全天で2番目に大きい星座ですが、スピカ以外は3等星より暗い星ばかりなので、女神の姿を想像するのは少し難しいかもしれません。明るめの3等星のポリマやビンデミアトリクスも手がかりにして、全体像をイメージしてみてください。
かみのけ座
「おとめ座」の北(上)、春の大三角から少し外に出たあたりに、微光星が集まっているところがあります。ここには「かみのけ座」という星座があります。歴史上実在した王妃ベレニケが神に捧げた美しい髪の毛が星座になったものとされていますが、髪そのものというよりもキラキラした髪飾りのような印象です。
「かみのけ座」の星の集まりは、空の条件が良ければ肉眼でもわかるほど明るい星団です。双眼鏡を使うと街中でも存在をとらえられるでしょう。春の大三角との位置関係を確かめながら探してみましょう。
おとめ座銀河団、M87銀河、M104銀河
「おとめ座」と「かみのけ座」の境界あたりには銀河が多数集まっています。星がたくさん集まった天体を「星団」と呼ぶのと同様に、銀河の集団は「銀河団」と呼び、この「おとめ座銀河団」の場合には銀河が1000個近くも含まれています。
おとめ座銀河団までの距離は約5900万光年、つまり光の速さで5900万年かかるところにあります。一般的な感覚では途方もなく遠いところですが、銀河団としては私たちから最も近く、様々な観測や研究の対象となっています。2019年4月に「人類史上初めてブラックホールの撮影に成功した」というニュースが発表されましたが、そのブラックホールが存在するM87銀河はおとめ座銀河団の中心にあります。
「おとめ座」や「かみのけ座」の領域にはこのほかにも非常に多くの銀河が存在しています。ほとんどは見かけ上とても暗いので、天体望遠鏡を使っても観察は難しいかもしれません。天体写真愛好家や天文台、宇宙望遠鏡などが撮影した画像を検索して、銀河の形状の違いなどを楽しんでみてください。たとえば「おとめ座」の南端には「ソンブレロ(帽子の一種)銀河」という愛称を持つM104銀河があります。
真夜中の星空
夜遅く帰ってくる人のため、ちょっと夜更かしの人のため、真夜中の星空をご案内しましょう。
図は5月中旬の深夜1時ごろの星空です。6月中旬の深夜23時ごろ、7月中旬の夜21時ごろにも、この星空と同じ星の配置になります(月が見えることもあります)。
「春の大三角」が西の空に移り、「春の大曲線」が北西から南西の空に大きなアーチを描いています。大三角と大曲線の両方に含まれる2つの1等星、アルクトゥールスとスピカの、色や明るさを見比べてみましょう。
反対の東の空には「こと座」のベガ、「わし座」のアルタイル、「はくちょう座」のデネブを結ぶ「夏の大三角」が高くなってきています。春から夏に三角形の引き継ぎをしているようなイメージですね。真南の空の低いところに見える「さそり座」のアンタレスの、赤っぽい輝きも目を引きます。空の条件が良ければ、夏の大三角から「さそり座」にかけて天の川も見えるでしょう。
すっかり暖かくなり、深夜の星空散歩もしやすいシーズンになってきました。ついつい夜更かししてしまいそうですが、無理は禁物です。今月ご案内した明け方の天文現象は、夜更かしではなく早起きしてご覧ください。
星空観察と撮影のポイント
星座や惑星、流星群などの天文現象の観察や撮影は、コツを抑えるとただ眺めるよりも広く深く楽しむことができます。
ここでは、天体の探し方からおすすめの撮影機材やテクニックまで、星空を楽しむうえで知っておきたいポイントをご紹介します。
カメラや双眼鏡を持って、美しい夜空に会いにいきましょう!
星空観察と撮影のポイント