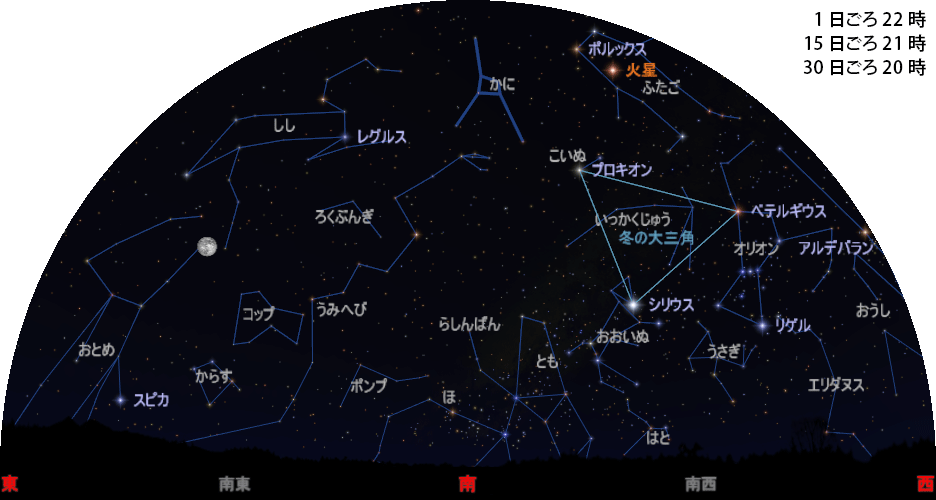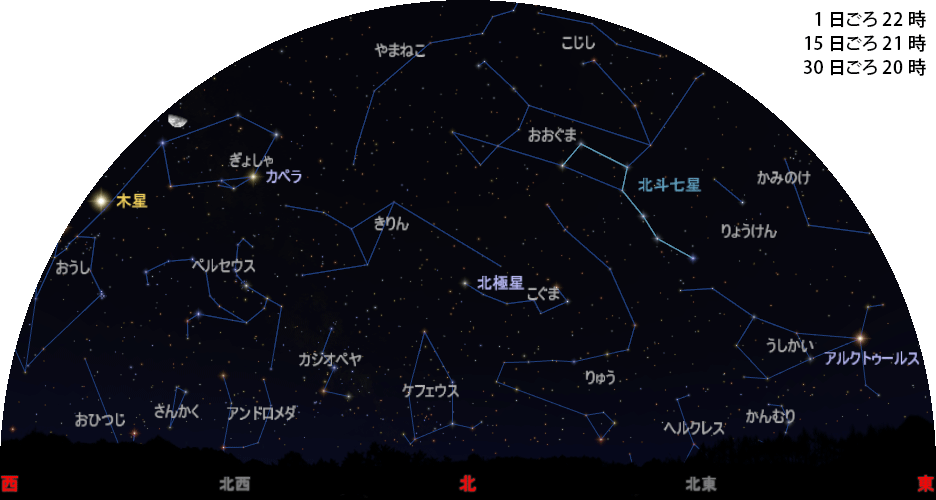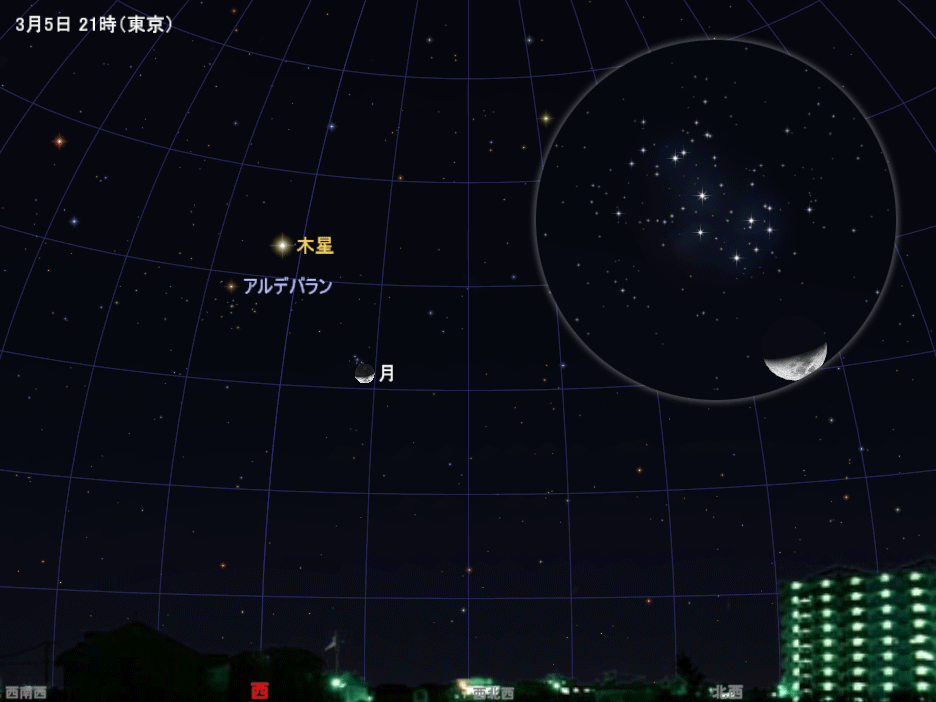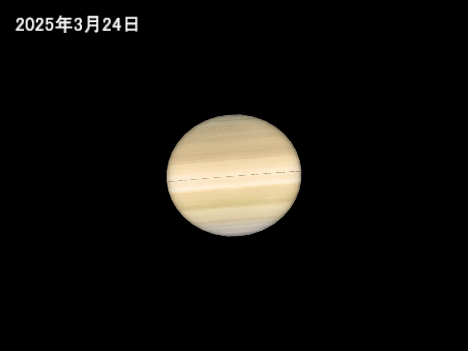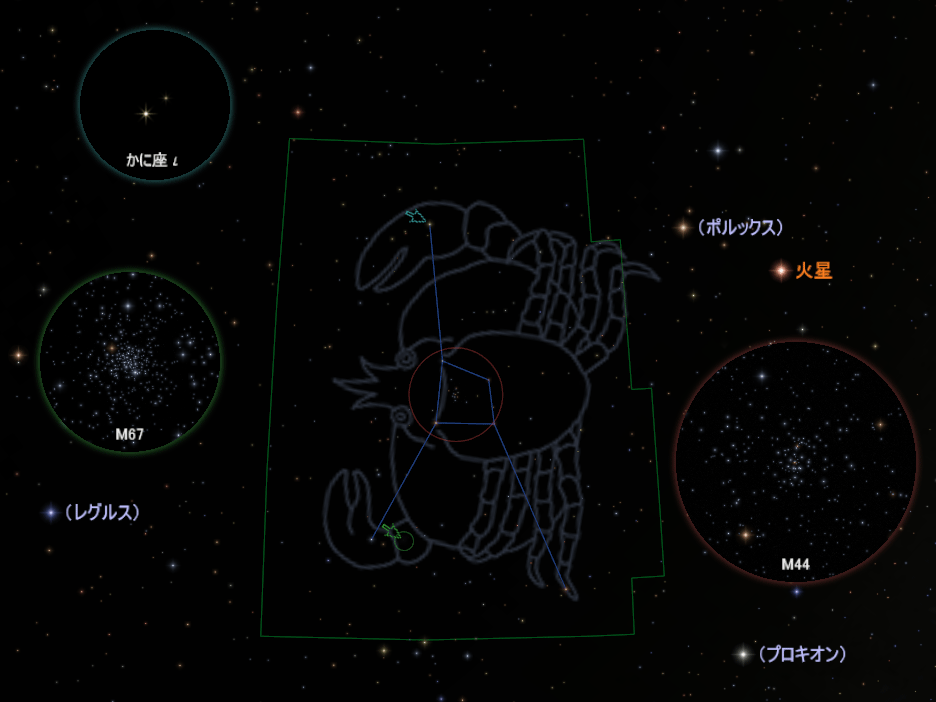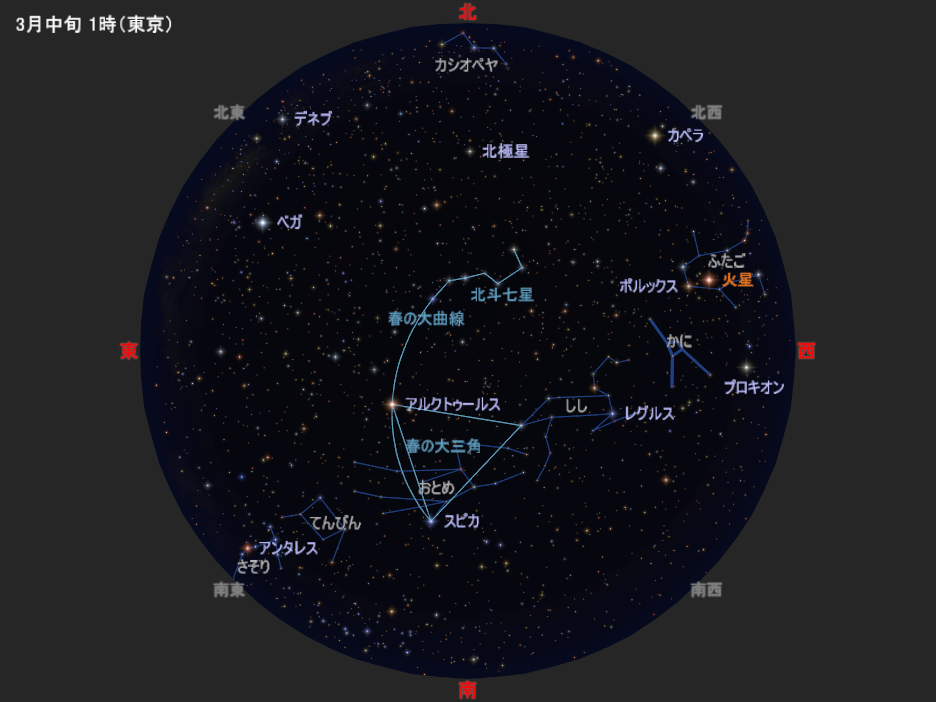2025年3月の星空
冬の明るい星々が西天に移り始め、後を追う春の星座たちが宵空に次々と姿を現します。金星はそろそろシーズンオフを迎えますが、木星と火星は引き続き見やすく、観察を楽しめます。土星の「見えない環」にも思いを巡らせてみましょう。
愛知県田原市 ロングビーチにて
太平洋を望む田原市ロングビーチでの撮影です。1月中旬の夜半過ぎには、春の代表星座でもある「しし座」が早くも昇ってきました。その下方には、かわいらしい「からす座」も顔を出しています。
2024年1月13日 1時19分
ニコン Z7+NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S(14mm、ISO6400、露出15秒×20枚を合成、f/2.8)
撮影者:石橋 直樹
3月の星空
天文カレンダー
| 1日(土) |
夕方、細い月と水星が大接近(「今月の星さがし」で解説) |
| 2日(日) |
夕方~宵、細い月と金星が並ぶ(「今月の星さがし」で解説) |
| 5日(水) |
21時~翌6日0時ごろ、プレアデス星団食(星団の星々が月に隠されます。「今月の星さがし」で解説) |
| 6日(木) |
夕方~翌7日未明、月と木星が並ぶ |
7日(金) |
上弦(日没ごろに南の空に見え、夜半ごろ西の空に沈む) |
| 8日(土) |
水星が東方最大離角(夕方の西の低空で比較的見やすくなります。「今月の星さがし」で解説)
深夜~翌9日未明、月と火星が並ぶ |
| 9日(日) |
夕方~深夜、月と火星が並ぶ
夕方~翌10日未明、月とポルックスが接近 |
| 12日(水) |
このころ、夕方の西の低空で水星と金星が並ぶ(「今月の星さがし」で解説)
夕方~翌13日明け方、月とレグルスが接近 |
14日(金) |
満月。次の満月は4月13日です
南北アメリカ、ハワイなどで皆既月食(日本ではほぼ見られません) |
| 16日(日) |
宵~翌17日明け方、月とスピカが大接近 |
| 20日(木) |
春分 |
| 21日(金) |
未明~明け方、月とアンタレスが大接近 |
22日(土) |
下弦(夜半に東の空から昇り、明け方に南の空に見える。下弦~新月は夜空が暗く、星が見やすくなります) |
| 24日(月) |
土星の環の消失(見かけ上、土星の環が見えなくなります。「今月の星さがし」で解説) |
29日(土) |
新月(下弦~新月は夜空が暗く、星が見やすくなります)
ヨーロッパなどで部分日食(日本ではまったく見られません) |
| 30日(日) |
このころ、夕方~未明に火星とポルックスが接近 |
3月の惑星
中旬ごろまで、夕方の西の低空に見えます。
日の入り45分後(東京で18時30分ごろ)の高度は7度前後とかなり低めですが、水星としては見やすいほうです。同じ夕空に見える金星を目印にすると位置がわかりやすいでしょう。西の空が開けたところで、双眼鏡で探してみましょう。「今月の星さがし」も参考にしてみてください。
1日に、月齢1の極細の月と大接近します。
中旬まで、「宵の明星」として夕方の西の低空に見えます。
日の入り45分後(東京で18時30分ごろ)の高度は、月初めは20度ほどありますが、15日ごろには5度未満と、日を追うごとにぐんぐん低くなっていきます。とても明るいので建物などに隠されていなければ簡単に見つかりますが、10日ごろ以降は見晴らしの良い場所で探してみてください。
2日に、月齢2の細い月と並んで見えます。また、12日前後に水星と並びます。
「ふたご座」にあります。20時ごろに頭の真上あたりに見え、3時ごろに沈みます。明るさは約0.1等級です。
宵から深夜の時間帯に高く昇っていて見やすい状態が続いていますが、地球との最接近から2か月以上が過ぎて遠ざかったため、やや暗く小さくなり、天体望遠鏡で模様を見るのはそろそろ難しそうです。特徴的な赤っぽい色や、「ふたご座」のポルックスとカストルとの並び方が変わっていく様子を、引き続き肉眼や双眼鏡で楽しみましょう。
8日の深夜から9日の未明にかけて、月齢9の上弦過ぎの月と並びます。また、9日の夕方から深夜にも月と並びます。
「おうし座」にあります。20時ごろに西の空に見え、日付が変わるころに沈みます。明るさは約マイナス2.2等級です。
火星と同じく見やすい状態が続いています。木星も地球との距離が(冬に比べて)大きくなっているのですが、木星はもともと大きく明るい天体なので、火星とは違って天体望遠鏡での観察はまだまだ楽しめます。縞模様や、木星を公転するガリレオ衛星の並び方が日々変わる様子を観察してみましょう。もちろん、冬の明るい星々と共に宵空で輝く光景を肉眼で眺めるのも面白いものです。
6日の夕方から7日の未明にかけて、月齢7の上弦の月と並びます。
太陽に近く見えません。次は4月末ごろから、明け方の東の低空に見えるようになります。
太陽に近いために観察はできませんが、見かけ上で環が消えてしまう「土星の環の消失」現象が起こっています。「今月の星さがし」を参考に、不思議な姿を想像してみましょう。
今月の星さがし
5日の宵から深夜、月がプレアデス星団の星々を隠す現象が見られます。双眼鏡で美しく面白い眺めが楽しめそうです。土星は太陽に近く観察はほぼ不可能ですが、実は「環が見えなくなる」現象が起こっています。
夕空で水星が見ごろ
太陽系の惑星の中で最も内側にあり太陽に近い水星は、地球から見るといつでも太陽の近くにあります。そのため、日の出の直前か日の入りの直後にしか見ることができず、観察のチャンスが限られます。
今月8日に、水星は見かけ上太陽から最も離れる最大離角という状態を迎え、「水星としては」見やすい条件になります。太陽の東側に離れるので「東方」最大離角と呼びますが、実際に見えるのは夕方の「西の空」です。日の入りの30分~45分後くらいに、西の空の低いところを探してみましょう。これより早い時間帯では空が明るすぎ、これより遅い時間帯になると水星が低くなってしまいます。
見かけ上で太陽から最も離れるとはいえ、日の入り45分後の高度は10度未満しかないので「見やすいとは言っても簡単ではない」状態です。見晴らしの良いところで、まず双眼鏡を使って探してみましょう。都合の良いことに、同じ西の空には宵の明星の金星が輝いているので、金星を目印にして水星の位置の見当を付けることができます。最大離角であることと目印の金星があることで、今月の中旬ごろまでは水星を見つける大チャンスです。ぜひ、探してみましょう。
5日宵~深夜 プレアデス星団の食
5日の22時ごろから24時(6日0時)ごろにかけて、上弦前のやや細めの月が、「おうし座」のプレアデス星団(すばる)の手前を通り過ぎて星々を隠す「プレアデス星団食(すばる食)」が起こります。日本の夜間に見られるものとしては昨年12月14日以来の現象です。
プレアデス星団は肉眼でも見える明るい天体ですが、今回のように月がすぐそばにあるときには月明かりに負けてしまうので、肉眼ではとても見づらくなります。双眼鏡や、低倍率の天体望遠鏡で観察しましょう。西から西北西の空が低いところまでよく見渡せる場所で眺めてみてください。
月の暗いほう(欠けている部分)の縁に星が吸い込まれるように消える様子や、星団の星々を背景に月が重なる光景を見ると、美しさや不思議さ、面白さなどいろいろな感情が湧いてくることでしょう。インターネットの中継などがあれば、観察場所によって重なり方が違う様子もわかるかもしれません。
今年はプレアデス星団食が4回も見られるのですが、時間帯や月と星団の重なり方といった条件からは、今回の現象が一押しです。ぜひ好天に恵まれて、「食」を楽しめますように。
土星の環の消失
3月中の土星は太陽に近いために観察することはほぼ不可能ですが、その土星で現在「環の消失」現象が発生しています。環が消えるとは、いったいどういうことでしょう?
土星の環は氷や岩石の粒が集まってできていて、土星の上空に広がっています。その幅は(明るいところだけでも)数万kmにも及びますが、一方で厚みは、最大でもほんの数百mほどしかありません。土星は地球から10億km以上も離れているので、これだけ遠いところから環を「真横に」見る状態になると、環が消えたようになってしまうのです。つまり、あくまでも見かけの話であって、環の実体がなくなってしまうわけではありません。
この「環を真横から見る状態」というのは、土星が太陽の周りを公転する約30年の間に2回発生します。土星は30度ほど傾いた状態で太陽の周りを回っているので、地球や太陽から見て大きく環が開いていることもあれば、環を真横から見る位置関係になって消えることもあるというわけです。
今シーズン、地球から見て土星の環が真横になるピンポイントのタイミングは3月24日ですが、実際には5月中旬ごろまで環はほとんど見えません(前述のとおり、太陽に近いので観察そのものも難しいです)。また、その後は順調に見やすくなるかというとそうでもなく、11月下旬ごろに再び非常に細くなります。このころには宵空に土星があるので、「環が見づらい土星」を観察できそうです。
環があってこその土星なのですが、15年に一度しかない現象となれば、環がない状態も面白いものだと思えるのではないでしょうか。次回ご自身の目で見るときにはどんな姿になっているかを想像しながら、今月は「観察できない土星の見えない環」に思いを巡らせてみてください。
今月の星座
かに座
6月下旬から7月中旬ごろに誕生日を迎える人の星座として名前が知られている「かに座」、見やすいのは初春の時期です。3月中旬の20時から21時ごろ、南の空の高いところに見えます。
「かに座」は一番明るい星でも3.5等級しかないので少し見つけづらい星座ですが、位置の見当を付けるのは簡単です。「ふたご座」のポルックス(今シーズンは火星も)と「しし座」のレグルス、「こいぬ座」のプロキオンという3つの1等星でできる三角形の中に、「かに座」の主な星々が広がっています。
暗めの星座ですが形は比較的わかりやすく、かにの甲羅にあたる小さな四角形が目印です。手足の星も見つけてみましょう。
プレセペ星団M44、散開星団M67
甲羅の4つの星の内側には、たくさんの星々が集まっています。「かいば桶(馬の餌桶)」という意味の語に由来する「プレセペ」という名前が付けられた散開星団(星の集まり)で、プレセペの南北にある星(2匹のロバ)が“かいば”を食べている姿に見立てたものとされています。メシエカタログという天体リストの44番目の天体なので「メシエ44/エム44」という番号でも知られています。
空の条件が良ければ肉眼でも存在がわかり、双眼鏡を使うとより簡単に見つけられます。ポルックスとレグルスの間あたりに双眼鏡を向けてみましょう。
また、プレセペ星団の南にはM67という別の散開星団があります。プレセペ星団ほどではありませんが、こちらも見やすい星団で、空の条件が良ければ双眼鏡ですぐに見つかります。2つの星団の明るさや星の広がり方などを見比べてみましょう。
二重星かに座ι星
かにの北のはさみの先にあるι(イオタ)星は、肉眼では1つにしか見えませんが、小型の天体望遠鏡で観察すると黄色っぽい4等星と白い6等星が並ぶ二重星であることがわかります。美しい色の対比を観察してみてください。
真夜中の星空
夜遅く帰ってくる人のため、ちょっと夜更かしの人のため、真夜中の星空をご案内しましょう。
図は3月中旬の深夜1時ごろの星空です。4月中旬の深夜23時ごろ、5月中旬の夜21時ごろにも、この星空と同じ星の配置になります(惑星は少し動きます/月が見えることもあります)。
西の低空に火星が輝き、南東の低空には「さそり座」の1等星アンタレスが見え始めています。2つの赤っぽい星が西と東でバランスを取り合っているかのようです。
その間に広がるのが春の星々たちで、とくに南の空に大きく広がる「春の大三角」が目立ちます。三角形を作る星の一つ、「うしかい座」のアルクトゥールスも、オレンジっぽい色味が美しい1等星です。3つの星の暖かな色合いに、春のぬくもりを感じられるかもしれません。北天高く昇った「北斗七星」も見ものです。
少しずつ寒さが和らいでくるとはいえ、深夜の空気はまだまだ冷たいものです。無理のない範囲で星空散歩をお楽しみください。
星空観察のワンポイントアドバイス
季節の星座や天体の動きを観察する星空観察。実は、ちょっとした知識や下準備で、得られる楽しさが大きく変わります。ここでは、流星の見つけ方や星座の探し方、場所選びや便利なグッズなど、星空観察をよりいっそう楽しむためのポイントをご紹介します。
星空観察のワンポイントアドバイス